マクナマラの誤謬(ごびゅう)とは、意思決定や政策評価において、「数値化できるもの」だけを重視し、「数値化できないが重要なもの」を軽視または無視する過ちを指します。この言葉は、アメリカの元国防長官ロバート・マクナマラに由来します。
マクナマラはフォード社出身で、統計や数値分析を重視する手法を用いて経営改革に成功しました。その後、ケネディ政権下で国防長官に就任し、ベトナム戦争の戦略を数値によって管理しようとしました。たとえば、ゲリラ兵の死者数(ボディカウント)や空爆回数などの「定量的指標」を基に戦況を評価しました。しかし、実際には敵の士気や南ベトナム民衆の心情、文化的背景などの「定性的な要素」を軽視したため、戦略は現実に即さず、結果としてアメリカは泥沼の戦争に陥りました。
この失敗は、「数値で測れるものしか存在しない」「測定できないものは重要でない」という誤った前提に基づいています。経済学者ダニエル・ヤンケロビッチはこれを批判的に「マクナマラの誤謬」と呼びました。
この誤謬は現代にも通じる重要な警告です。たとえば教育、医療、福祉、ビジネスの現場でも「KPI」や「成果主義」に偏りすぎると、人間の感情や創造性、倫理といった「数値化しにくいが重要な価値」が損なわれるおそれがあります。たとえ数値では「成功」しているように見えても、実際の人間関係や社会の健全性は損なわれているかもしれません。
マクナマラの誤謬は、「測れること」と「本当に重要なこと」は必ずしも一致しないという本質的な問いを投げかけています。物事を深く理解し判断するには、数値に現れない背景や文脈、現場の声にも耳を傾ける姿勢が不可欠です。

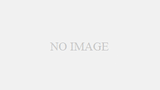
コメント